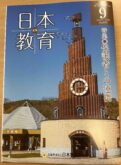先日、とある教育委員会の方から嬉しいメールが届きました。メールの内容は講演会のご依頼だったのですが、私のブログを読んでわざわざご連絡をくださったとのこと。講演のお仕事も嬉しかったのですが、何より嬉しかったのはブログの情報発信がちゃんと現場の先生方に届いていたことです。教育コンサル冥利に尽きます。 【スポンサードリンク】 子供たちの未来のた …
Read More »保護者向けの記事
11月20日に福島にてロボット・航空宇宙フェスタが開催
ロボット・航空宇宙に関するリアルイベントの紹介です。11月19日(金)、20日(土)に福島県郡山市にて「ロボット・航空宇宙フェスタふくしま2021」が開催されます。ロボット・航空宇宙に関する様々な展示や体験イベントが開催されます。子ども向けのイベントも豊富で、傘袋ロケット作り体験や土星の模型作成、ドローン操作体験、プログラミング教室など沢 …
Read More »ICTが日常化している学校の見分け方
勤務校にICT活用が定着していることをどう判別すれば良いでしょうか。志望校の学校でICT活用がどの水準が見極めるためにはどうすれば良いでしょうか。ICTが日常化している学校の見分け方は、実は休み時間にあります。 【スポンサードリンク】 ICTを文房具として扱っているか コロナによる一斉休校をきっかけに、多くの中学校・高等学校では生徒1人1 …
Read More »私立学校の授業視察
今日は私立学校の授業視察のお仕事に行ってきました。授業視察といっても単に授業を見学するのではなく、学校が教育の質を向上させていくために「授業の品質認証」を行う業務です。専門用語で「アクレディテーション」と呼びます。今回は21世紀型教育機構に加盟している私立中高一貫校のひとつで、アクレディテーションのための授業視察を行わせていただきました。 …
Read More »保護者会講演
本日は首都圏模試センター小6「合判模試」の試験会場校である千葉明徳中学校・高等学校にて、小学生の保護者を対象にした講演をさせて頂きました。千葉明徳さんで保護者会講演をするのは2017年振りでしたので、久しぶりに公園ができて嬉しく思っています。これから受験シーズンが到来しますので、頑張っている受験生たちのためにも感染が拡大しないことを祈って …
Read More »【来春公開】目の見えない男の子と、耳の聞こえない女の子と、障がいのある神様のインクルーシブな読み聞かせムービー
私がサポーターをしている「ホワイトハンドコーラスNIPPON」から、素敵な絵本『ミルとキクとポッシボ』の企画が発表されました。『ミルとキクとポッシボ』の公式ホームページがオープンしただけでなく、絵本の予告編ムービーも公開されました!どちらも素敵な内容で、子供たちにも人気があります。興味のある方は、ぜひご覧になってください。 【スポンサード …
Read More »手作り味噌が出来ました!
今日は日記系の記事です。今年の2月にブログに書いた「子供も楽しめる手作り味噌の仕込み」のその後です。お味噌を寝かしてから早8ヶ月が経ちましたので、先日ワクワクしながら思い切って蓋を開けてみました。 【スポンサードリンク】 手作り味噌の開封の儀 手作り味噌を仕込んだ時の記事はこちらになります。 手作り味噌は夏に最も発酵が進むため、ひと夏を越 …
Read More »「親子で学ぶ星と宇宙〜秋の星座と太陽系」(北区中央公園文化センター子ども講座)を開催しました
本日、北区の中央公園文化センターにて「親子で学ぶ星と宇宙〜秋の星座と太陽系」を開催しました。新型コロナ感染症対策のため、定員はコロナ前の半分以下の16組でしたが、ありがたいことに満員御礼で、35名の親子に参加していただきました。今年の夏はコロナの影響で中央公園文化センターでも子供向けイベントがほとんど中止になってしまったそうです。久しぶり …
Read More »教育誌「ShuTOMO(しゅとも)」に寄稿したICTの特集記事が掲載されました
教育誌「ShuTOMO(しゅとも)」に寄稿した記事が2021年10月3日号に特集として掲載されました。特集記事のタイトルは、「ICT教育が生む新しい資質と能力〜世界基準の学びにおけるICT活用とは〜」です。今回の記事では「コロナ禍で加速したICT活用の格差」や「ICT端末の持ち帰り問題」、「ICT先進校で共通している2つのポイント」、「家 …
Read More »教育月刊誌「日本教育」に寄稿した記事「オンライン部活の普及」が掲載されました
教育月刊誌「日本教育」に寄稿した記事が令和3年9月号に掲載されました。記事のタイトルは、「オンライン部活の普及」による部活動の個別最適化、です。今回の記事では、私たちが取り組んでいるオンライン部活の意義について、教員の働き方改革と「部活動の個別最適化」の観点から紹介させていただきました。教育月刊誌「日本教育」とは、全国の校長会やPTA団体 …
Read More » 福原将之の科学カフェ AI時代の教育を、現場から考える
福原将之の科学カフェ AI時代の教育を、現場から考える