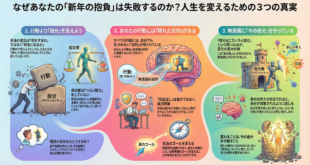東京大学の学内広報に掲載された、経済学研究科・小川光教授のエッセイをご紹介します。エッセイでは、学外の修士2年生から研究評価を依頼された際のエピソードが綴られています。注目すべきは、この学生が経済学をほとんど学んだことがないにもかかわらず、専門外の経済学分野において「AIとの対話だけでどこまでの研究が可能か」を1年間かけて検証したという点です。その結果、彼の研究は着眼点、新規性、データの質いずれにおいても、フィールドトップの学術誌に挑戦できる水準に達していたといいます。
生成AIの登場により、既存の様々な業界が否応なしに変質していく――小川教授のエッセイは、その現実を改めて実感させてくれるものでした。興味のある方は、ぜひリンク先からエッセイ本文をご覧ください。
お勧めエッセイ
お勧めエッセイはこちらです。
学外のとある修士2年生の学生から、研究を評価してほしいと頼まれました。彼がやっているのは、私が専門とする研究分野のある仮説をデータによって検証する内容でした。読んでみたところ、経済学の五大誌は難しいにしても、着眼点、新規性、データの質などから、フイールドトップの学術誌に挑戦できる水準にあると感じました。
驚かされたのは、彼が経済学を専攻する学生ではなく、それどころか経済学をこれまでほとんど学んだことがないという点です。彼の関心は技術の新領域への応用、特に「生成AIの新活用」にあり、専門外である経済学という分野で、AIとの対話だけでどこまでのレベルの研究ができるかを1年間かけて試してみたというのです。研究のアイデア出し、先行研究のレビュー、理論モデルと仮説の構築、データの探索と収集、計量ソフトを用いた分析、図表の作成、英語論文化に至るまで、さまざまなAIツールを組み合わせながら、ほぼ独学で試しているとのことでした。
 福原将之の科学カフェ 「福原将之の科学カフェ」では、学校の先生や小学生・中学生・高校生の保護者に向けて、教育に関する情報を発信しています。カフェで読書をするような気楽な気持ちでお楽しみください。
福原将之の科学カフェ 「福原将之の科学カフェ」では、学校の先生や小学生・中学生・高校生の保護者に向けて、教育に関する情報を発信しています。カフェで読書をするような気楽な気持ちでお楽しみください。